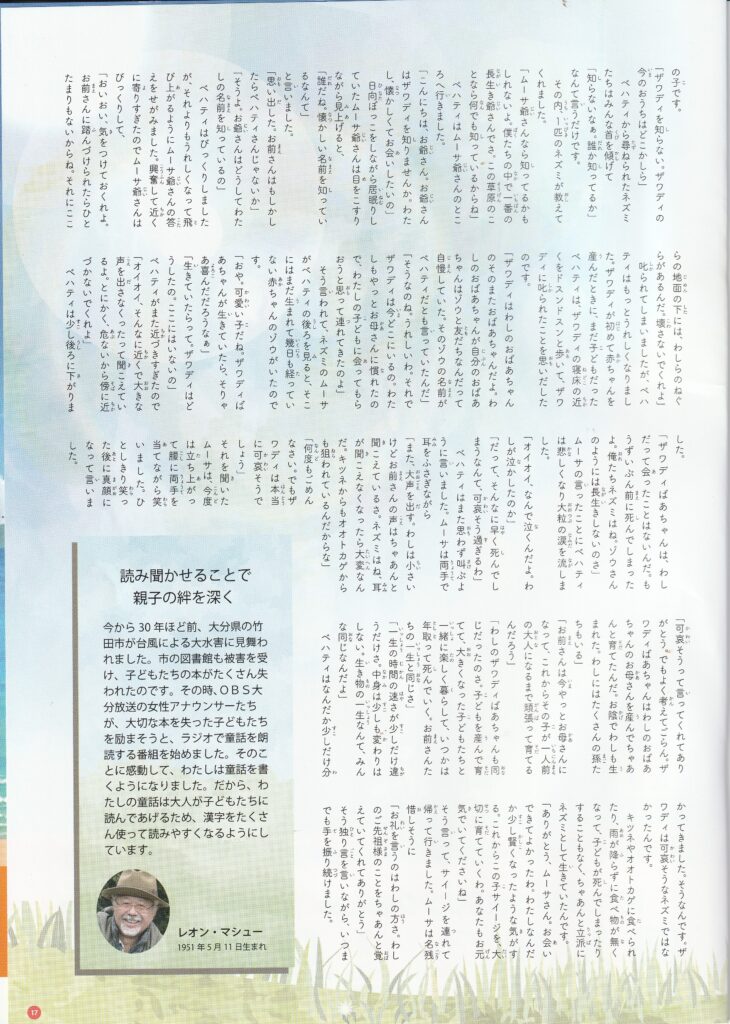①少子化対策
まず間違ってはいけないのは子どもはその存在が社会全体の活力のバロメーターではあっても、年寄りの生活保障のためや、企業にとって必要な労働力と消費市場の確保のための存在ではないということだ。「高齢者のために子どもを産んでくれ」「企業の労働力確保のために子どもを産んでくれ」「GDPを目減りさせないために子どもを産んでくれ」などという考えは、それそのものが戦前の「産めよ増やせよお国のため」と同じ、軍国主義を肯定するものだと、わたしは考えている。
戦争中の産めよ増やせよキャンペーン、敗戦直後のベビーブーム、丙午問題など種々の要因が重なって、日本の人口増加は急激と同時に歪なものになった。しかし、今のキノコ型人口ピラミッドを構成する高齢者層はあと30年もすればいなくなる。ほんの30年みんなで我慢すれば済む問題であり、そのために子どもを産んで欲しいなどという論調は言語道断である。
安定的な人口ピラミッドとはお寺の鐘型が良いとされている。あと30年で人口は7千万人前後まで減ると覚悟しなくてはならないが、そのかわり日本もその安定型の人口ピラミッドも実現できるのだ。今、目先の不安に駆られて、苦しみを先延ばししようとする無能な政治家と高級官僚たちにはお引き取り願わなくてはならない。現在のキノコ型人口構成になることは1970年代から専門家の言ってきたことであり、それに一顧だにしてこなかったのは誰なのか。
人口が減れば就労人口も経済市場も縮小するというが、これにも騙されてはいけない。人口が減ってGDPが縮小しても、一人当たりのGDPを確保、あるいは増やすことは可能なのだ。人口が減ってもそれだけでわたしたち一人ひとりの生活レベルは低下することはない。英仏伊などの国々の人口と経済力を考えれば容易に証明できることである。
誰が自分の親や祖父母でもない高齢者の生活を支えるためと言われて子どもを欲しがるだろうか。家業の後継確保というのならともかく、誰が企業のために企業に雇用される労働者を産みたいだろうか。企業の作った製品を買う市場の確保のために子どもを産みたいと思うだろうか。
子どもを産むか産まないかは個人の選択権であり、憲法で保障された究極の基本的人権である。現状の不確定要素の多い国内社会、未来に不安が多い国際社会下で、子どもは産みたくないという判断をすることを攻めることはできない。むしろ、政治家は須くそう言われる世の中にしてしまった自分たちを自省し、子どもを産んでもいいと思える社会の実現を考えるべきだろう。
では何をするべきか。わたしは少子化対策とは産みたいと思ってもらえる環境づくり、産もうと努力する人たちへの支援、生まれた子どもがスクスクとイキイキと育っていける環境づくりに尽きると考える。産みたいと思う世代への周産期医療支援、生まれた子どもの社会全体、地域コミュニティー全体での子育て支援、子どもの心身ともの成長支援である。「産んだらなんぼやる」「3人目からは生活保障しましょう」というニンジン政策ではない。それはそれであってもいいのだが、必要なのは社会全体での支援である。その社会全体の支援というのは政府や自治体だけの支援というのではない。繰り返すが子どもが育つ環境とは地域であり、地域のコミュニティ―であり、子どもが育つ場所の自然環境保全である。
「だからどうしようというのだ」と思っている方にはお願いした。是非、最後の⑧まで我慢して読んで頂きたい。その上で、あなたの思う人に投票していただければ、わたしの望むところだ。
わたしたち一人ひとりの、この国の未来に対する責任感の在りようが選挙の投票行動を通して問われているのだから。